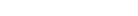コラム
- コラムトップ
- 顧客に響くベネフィットとは?マーケティングで成果を上げる伝え方と事例紹介
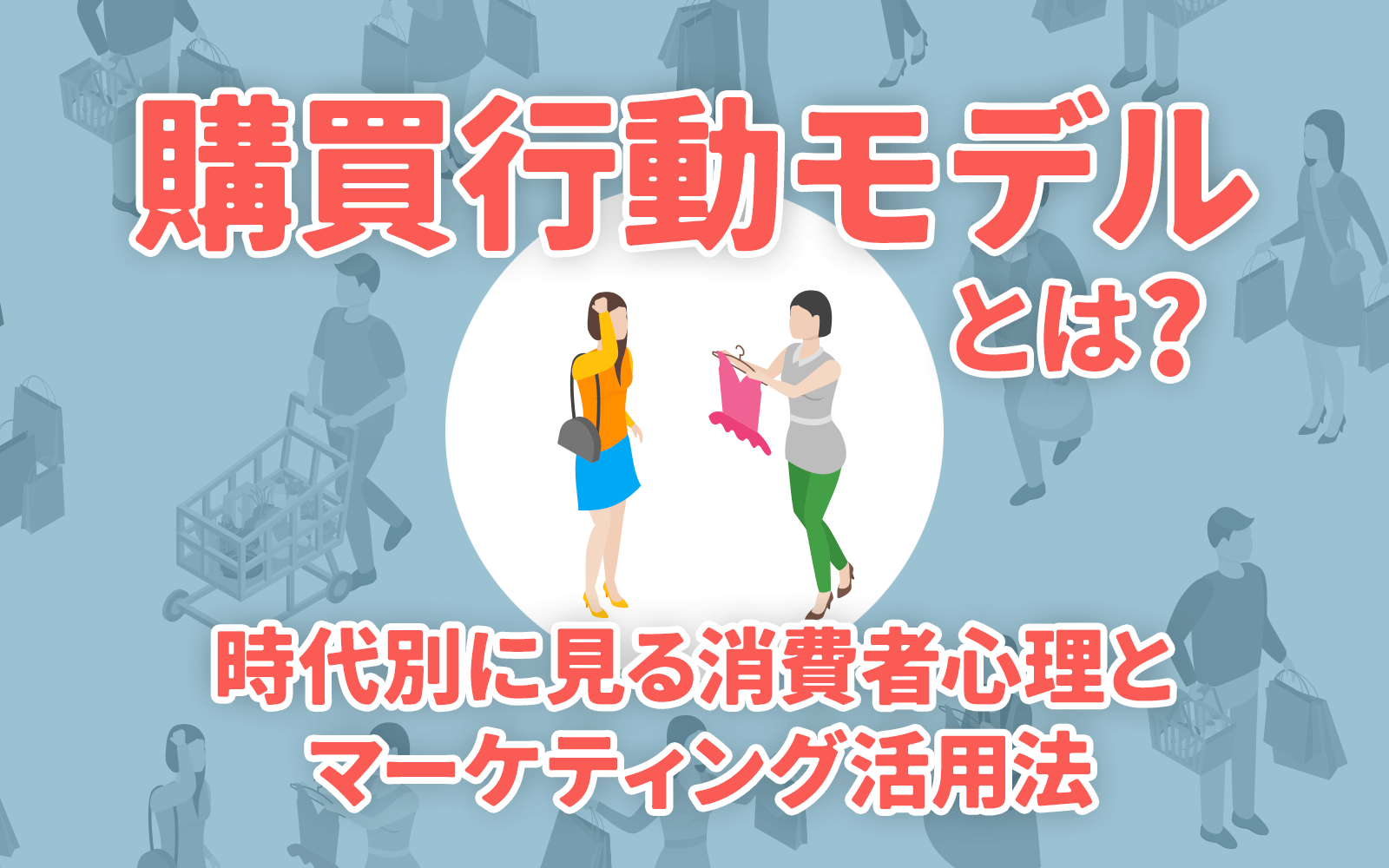
購買行動モデルとは?時代別に見る消費者心理とマーケティング活用法
「なかなか広告の効果が出ない」「どうすればお客様に選ばれるのか分からない」
広告を出稿する広告主様の中には、こんな悩みを抱える会社も少なくありません。
こうした課題の解決に役立つヒントとなるのが「購買行動モデル」です。購買行動モデルとは、消費者が商品を認知してから購入、さらには他者への共有に至るまでのプロセスを体系的に捉えたものです。このモデルを理解することで、広告や販促の施策がより的確になり、売上や利益の向上にもつながる可能性があります。
ただし、時代の変化に伴い、消費者の購買手段や意思決定のプロセスは多様化しています。そのため、購買行動モデルにもさまざまな理論やアプローチが存在しているのが現状です。
本記事では、各時代の購買行動モデルとその活用方法をわかりやすく解説します。
購買行動モデルとは?
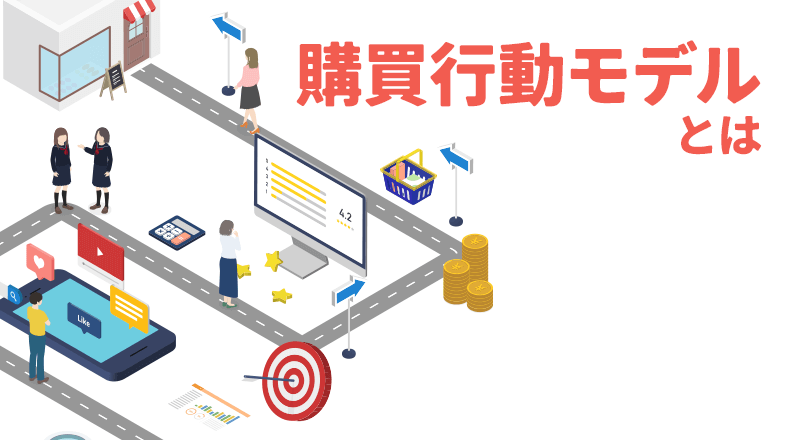
購買行動モデルとは、消費者が商品やサービスを購入(または契約)するまでの態度変容を段階的に整理したフレームワークです。記事を読んでいる皆さんも、日常で意識はしていないかもしれませんが、とある商品がほしいと思った際には、商品を知ったタイミングから購入に至るまでの間に、様々な心理的変化をたどっているはずです。
マーケティングの効果を高めるためには、このモデルに沿って消費者の心理や行動を理解することが不可欠とされています。心理状態の推移を理解できれば、最適な集客方法やPR方法を検討することができるためです。よく活用されるシーンとしては、マーケティング担当者がユーザーのカスタマージャーニーマップを作成する際に、この購買行動モデルが取り入れられています。

カスタマージャーニーとは?顧客の行動を可視化するメリットと手順
顧客起点の事業、マーケティングを考える上で欠かせない「カスタマージャーニー」。言葉は知っているけど具体的にどういうものか分からない、何のメリットがあるのか分からないから作れない、等のマーケティング担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そうは言っても、ここ数十年の間に購買行動は複雑化しており、その度に様々なモデルが誕生しています。数ある購買行動モデルの中から、自社の商材やビジネスモデルと合致するものを見つけ、それに沿ったマーケティング施策を打つことが肝要です。
ここからは、時代の流れに沿って提唱されてきた様々な購買行動モデルをご紹介します。
時代ごとの購買行動モデル
購買行動モデルは、時代ごとの技術やメディア環境に応じて進化してきました。ここでは、マスメディア時代・インターネット時代・SNS時代の3つに分けて、それぞれの代表的な購買行動モデルをご紹介します。
■マスメディア時代の購買行動モデル

マスメディアとは、不特定多数の大衆に対して情報を伝達するメディアのことです。テレビ、新聞、ラジオ、雑誌などが該当します。インターネットがまだ発展していない時代には、企業はマスメディアを通じて情報発信することが主な消費者との接点でした。逆に消費者目線から言えば、マスメディアの情報で商品を知って、小売店や店舗、もしくは電話注文などで購買行動をするというのが一般的な時代になります。
この時代には、企業からの情報を起点にして購入まで至る、シンプルな態度変容を表す購買行動モデルがマーケティングに使われています。
AIDA(アイダ)
AIDAは、最も単純で古典的な購買モデルです。
消費者の購買行動は、以下の4つの段階で構成されていると説明しています。
- 注意(Attention)・・・商品/サービスについて知る
- 興味(Interest)・・・商品/サービスに興味関心を持つ
- 欲求(Desire)・・・商品/サービスが欲しくなる
- 行動(Action)・・・商品/サービスを買う
この後様々なフレームワークが誕生しますが、このAIDAをもとにした考えのものも多く、購買行動モデルのいわば原点とも捉えられます。現在でも顧客の心理的な過程をシンプルに捉えるために、有効な考え方です。
- 活用できる商材
- BtoC商材全般、特に洗剤、飲料、日用品、雑貨、ファストフードなど主に店頭で即決・感覚的に買われる商材など
AIDMA(アイドマ)
AIDMAは、AIDAに「記憶(Memory)」が加わった購買モデルです。
- 注意(Attention)・・・商品/サービスについて知る
- 興味(Interest)・・・商品/サービスに興味関心を持つ
- 欲求(Desire)・・・商品/サービスが欲しくなる
- 記憶(Memory)・・・商品/サービスを思い出す
- 行動(Action)・・・商品/サービスを買う
AIDMAでは、消費者は広告などで商品/サービスに関する情報を見た後に記憶に留める段階があり、購入のタイミングを計ったり、やはり自分に必要な商品だと感じた段階を経て、購買の行動を起こすという流れが強調されています。このモデルをマーケティングに活かすには、ほしいという欲求を抱かせた後に、いかに情報を記憶させるか・印象に残すかが重要と言えます。逆を言えば、この段階で商品/サービスのことを忘れられてしまうと、購入まで繋がりません。インパクトのある広告で商品を長く覚えてもらったり、時間が経過した際に再度商品を思い出してもらう工夫を施すなど、様々な施策に活かすことができます。
- 活用できる商材
- BtoC商材全般、特に家電、化粧品、アパレル、自動車などの高関与商品
AIDCAS(アイドカス)
AIDCASは、AIDAに「確信(Conviction)」と「満足(Satisfaction)」を加えたモデルです。
- 注意(Attention)・・・商品/サービスについて知る
- 興味(Interest)・・・商品/サービスに興味関心を持つ
- 欲求(Desire)・・・商品/サービスが欲しくなる
- 確信(Conviction)・・・商品/サービスが必要と確信する
- 行動(Action)・・・商品/サービスを買う
- 満足(Satisfaction)・・・商品/サービスに満足する
消費者が納得してモノを買い(行動)、その後「満足」段階まで心理的工程があることを理解できれば、次の購買やリピート購入につなげる施策を検討することができます。そこまでを意識したモデルが、このAIDCASです。つまりAIDCASは、新規顧客獲得だけでなく、リピーター獲得やファン化までを見据えたマーケティング施策を検討したい場合に役立ちます。
リピーターやファン化はLTVを上げる上で有効な考え方です。ある程度新規購入や自社会員が増えてきたら、ぜひ次のステップとしてリピート購入やLTVの上昇を狙ったマーケティングを行ってみてください。また、工夫すれば法人向けサービス(BtoB)にも活用できます。
- 活用できる商材
- BtoC商材全般、特に住宅、車、リフォームなど慎重な意思決定が必要な高単価商品や保険、金融商品など信頼が必要な商品、化粧品・食品等のリピート購入が狙える商材(消耗品)、BtoB商材
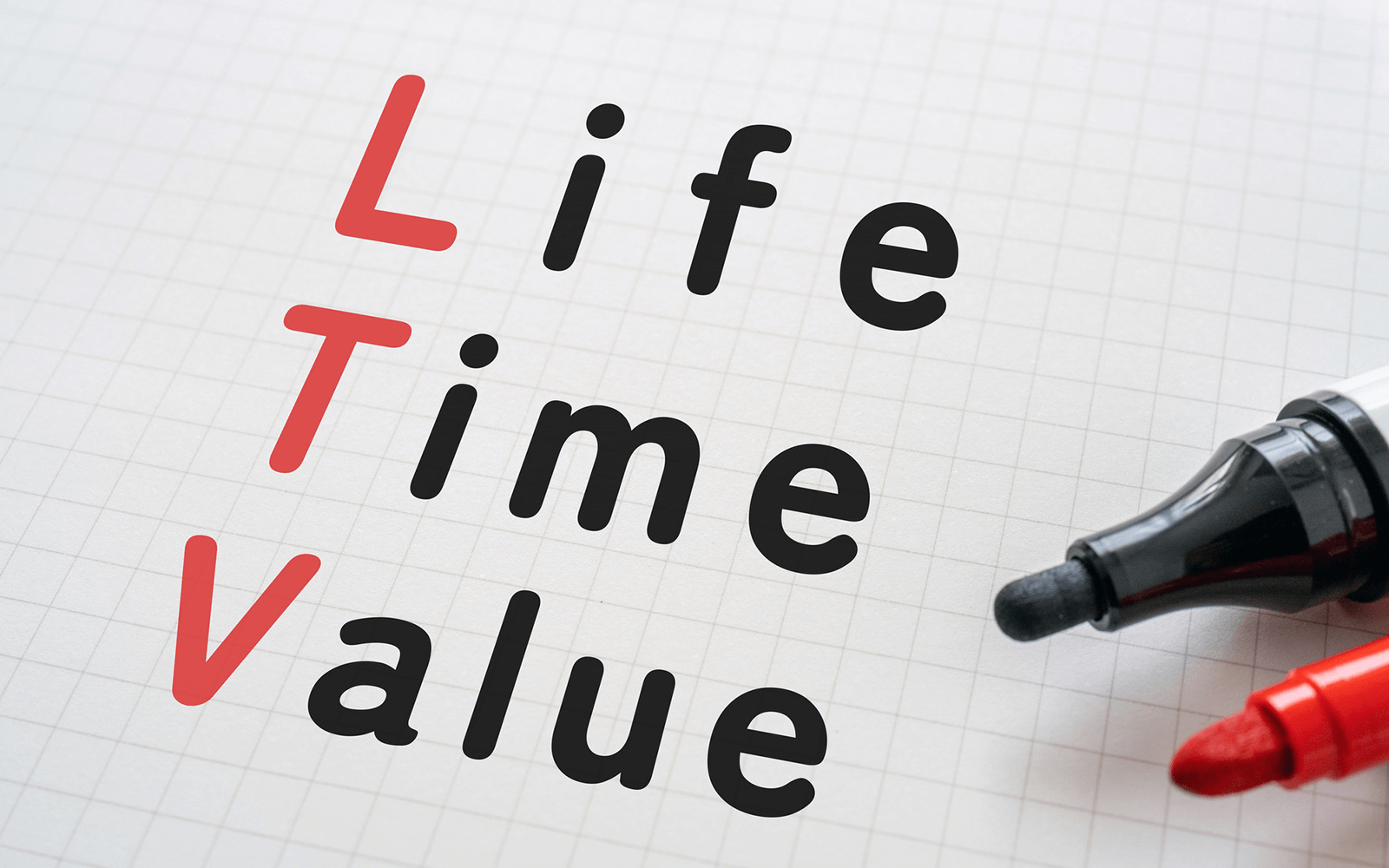
LTV(顧客生涯価値)って何?計算方法や活用方法をご紹介
ビジネスを行う上で重要視される「LTV」。Web広告にも深い関わりがあり、重要な役割を持ちます。今回は言葉の意味や重要性、Web広告でどのように活用できるのかを説明させていただきます。
■インターネット時代の購買行動モデル

1990年代後半〜2000年代初頭にはインターネットが急速に普及しました。インターネットは消費者の購買行動にも大きな変化を与えることになります。消費者は、マスメディアから一方的に発信される情報を受け取るだけでなく、自ら能動的に情報を取得することが可能になりました。合わせて、人と人がつながって情報共有することも可能になります。また、ネット通販による購買も当たり前になり、店舗に足を運ばなくても商品やサービスが買える時代に突入します。

Web広告とは?12の種類とその特徴をご説明
Web広告は広告の一種で、ネット上のWebメディアやアプリ等に掲載される広告の総称です。インターネット広告、オンライン広告などとも呼ばれます。
この頃になると、従来の購買行動モデルだけでは多様化する消費者の意思決定プロセスを把握しきれなくなり、新しいモデルが次々と登場します。代表的なものを4つご紹介します。
AISAS(アイサス)
AISASは、インターネット検索が行動の中心になるモデルです。以下の5つの行動変容で消費者心理を表しています。
- 注意(Attention)・・・商品/サービスについて知る
- 興味(Interest)・・・商品/サービスに興味関心を持つ
- 検索(Search)・・・商品/サービスについて情報収集する
- 行動(Action)・・・商品/サービスを買う
- 共有(Share)・・・商品/サービスを他者に紹介する
商品やサービスを知り、興味関心を持ったら、検索して情報収集を経て購入、そして、気に入ったら他者にシェアするという一連の購買行動に対応しています。情報収集とは、例えば口コミの閲覧や他社製品との比較など、様々な検索行動が含まれています。皆様も、購入する前にインターネットでどういう商品か?を調べてみる行動に、心当たりはあるのではないでしょうか。
- 活用できる商材
- BtoC商材全般、特にネット検索との相性が良い商材、EC通販で購入できる商材
AISCEAS(アイシーズ/アイセアス)
AISCEASは、AISASのモデルに「比較(Comparison)」「検討(Examination)」を加えたモデルです。
- 注意(Attention)・・・商品/サービスについて知る
- 興味(Interest)・・・商品/サービスに興味関心を持つ
- 検索(Search)・・・商品/サービスについて情報収集する
- 比較(Comparison)・・・複数の商品/サービスで比較する
- 検討(Examination)・・・商品/サービスの購入を検討する
- 行動(Action)・・・商品/サービスを買う
- 共有(Share)・・・商品/サービスを他者に紹介する
心理・行動過程をここまで細分化して捉えるモデルは、特に検討期間が長い商材に有効です。例えば車や家など簡単に決められるものでない場合、この比較・検討期間中の消費者に対して適切なコミュニケーションをしっかり取れれば、最終的に自社商品を選んでもらえる確率をUPすることができます。
- 活用できる商材
- 複数候補で比較検討が多い商材(旅行、不動産、保険、自動車、パソコン、塾など)
DECAX(デキャックス)
DECAXは2015年に(株)電通様によって提唱された、コンテンツマーケティングに対応した購買モデルです。前述のとおり、インターネットの普及で消費者は自ら情報を探しに行くことができるようになりました。そこで、企業が発信する情報で商品を知るという機会だけでなく、自ら探し「発見する」というきっかけ起点の購買行動が捉えられる、革新的なモデルが誕生しました。
- 発見(Discovery)・・・商品/サービスを見つける
- 関係構築(Engage)・・・商品/サービスや企業と関係を深める(フォローやお気に入りなど)
- 確認(Check)・・・商品/サービスや企業の情報を確認する
- 行動(Action)・・・商品/サービスを買う
- 体験と共有(eXperience)・・・商品/サービスの体験をシェアする
専門的な用語を使うと、企業の「プッシュ型」のメッセージきっかけが多かったこれまでの時代から、消費者側から企業や情報に接触してくる「プル型」の購買行動モデルが誕生した、とも言えます。
- 活用できる商材
- BtoC商材全般、特にEC、D2C、SNSなどで集客・販売に力を入れている企業
MOT(モット)
MOTは、「Moment of Truth」の略称で、日本語では「真実の瞬間」と訳せます。赤字であったカンジナビア航空を1年で立て直した元CEOヤン・カールソン氏が提唱した概念で、「サービススタッフが実際に顧客と接するたった15秒(瞬間)の接客態度が、企業の成功を左右する」として、その短い瞬間の顧客満足度を最大限上げることが重要、と唱えました。つまりMOTは、消費者が商品やサービスを「目にする瞬間」、「実際に使った瞬間」に着目し、その瞬間をどうデザインするかを重視したモデルになります。一瞬の接客やインプレッションによって購入や商品/サービスの質を判断されるので、そこをうまくプロモーションに活かしていきましょうという考え方です。
このMOTをベースとしたモデルには、以下の4つのモデルがあります。
- ZMOT(Zero MOT)・・・商品/サービスに実際に触れる前、オンラインで積極的に情報収集し、店舗に足を運ぶ以前にすでに購入の意思決定をするという理論。
- FMOT(First MOT)・・・店頭で商品/サービスを初めて目にした最初の瞬間。商品棚を見て3-7秒の間に、展示やパッケージの印象で購買を決定するという理論。
- SMOT(Second MOT)・・・商品/サービスを購入後、実際に使った体験を通してリピートするかどうかを決める瞬間のこと。
- TMOT(Third MOT)・・・商品/サービスの利用を通じて、企業やブランドのファンになるかを決める瞬間のこと。
このように消費者との接点は分断的に捉えることができますが、言い換えると顧客は商品/サービスを購入〜利用する体験の中で、計4回評価するタイミングがあると言い換えることもできます。それぞれの瞬間(接点)ごとに、より良い印象を残す適切な施策を打っていくことが重要とされています。
- 活用できる商材
- BtoC商材全般
■SNS時代の購買行動モデル

SNSが普及して一般化すると、従来のフレームワークではカバーしきれない「共感」や「拡散」といった新たな要素が重要視されるようになります。企業のPRからだけでなく、インフルエンサーや口コミなど他者の意見に基づく意思決定も多くなるのが大きな特徴と言えます。SNSを前提とした購買行動モデルとしては、次のようなものが活用されています。

SNS広告の基本と成功ポイント|主要6大SNSの違いも解説
今やWebマーケティングに欠かせない存在となったSNS。企業の活用事例としては、公式アカウントを開設して情報を発信する方法が一般的ですが、実は広告を出稿するという選択肢もあることをご存じでしょうか?
VISAS(ヴィサス)
VISASは口コミの影響で購入、契約などのアクションを起こす様子をモデル化したものです。以下の5つの段階で構成されています。
- 口コミ(Viral)・・・SNSの投稿や口コミで商品/サービスを知る
- 影響(Influence)・・・口コミの影響を受ける
- 共感(Sympathy)・・・口コミに共感する
- 行動(Action)・・・商品/サービスを買う
- 共有(Share)・・・商品/サービスを他者に紹介する
広告などの企業からの情報発信ではなく、一般消費者の口コミやインフルエンサーの言葉に共感して購入を決める、という体験は、まさにSNSの普及を通じて広がりました。VISASはそれをうまく説明した購買行動モデルになっています。
- 活用できる商材
- BtoC商材全般、特にSNSとの親和性が高い低価格~中価格ほどの商材(ファッション、飲食店、化粧品、コスメなど)
SIPS(シップス)
SIPSはVISAS同様、企業発信よりもユーザーのリアルな声や反応を重視するモデルです。以下の4つによって構成されています。
- 共感(Sympathize)・・・情報や発信元に共感する
- 確認(Identify)・・・商品/サービスについて確認する
- 参加(Participate)・・・いいねやシェアなどでPRに参加する
- 共有+拡散(Share&Spread)・・・シェアした情報が共有、拡散される
これまでの購買行動モデルとは異なる大きな特徴として、必ずしも「購入(Action)」をゴールとしていないという点があります。そのため、情報拡散や認知度を上げることを目的としたマーケティングにも活用できるフレームワークとなっています。「参加」や「共有」「拡散」をうまく用いれば、消費者・インフルエンサーを巻き込んでPRでき、商品情報の循環や信頼性の上昇など世間に好影響を与えられます。
- 活用できる商材
- 共感を得やすい商材(推し活グッズ、音楽、ファッションなど)
ULSSAS(ウルサス)
ULSSASは、SNSマーケティングの(株)ホットリンク様が提唱する購買行動モデルです。UGC(User Generated Content)という一般ユーザーが投稿したSNSコンテンツを起点に、消費者が“発信者”として商品価値を広げていく様子をモデル化しています。
- 認知(User Generated Contents)・・・UGCで商品/サービスを知る
- 好印象(Like)・・・いいねや拡散を通してエンゲージメントが高まる
- 検索1(Search)・・・SNSで情報を検索する
- 検索2(Search)・・・検索エンジンで情報を検索する
- 行動(Action)・・・商品/サービスを買う
- 拡散(Spread)・・・SNSや口コミサイトで情報を拡散する
ULSSASは1から6への一方通行ではなく、「6.拡散」がまた「1.認知」や「2.好印象」につながるサイクル型の購買行動モデルです。この循環がうまく回れば、企業側はあまり広告費をかけることなく商品/サービスのPRが広がっていくため、SNSは様々な企業がマーケティングツールの一つとして力を入れて活用しています。
- 活用できる商材
- SNSと親和性の高い商材(化粧品、コスメ、雑貨、ファッション、飲食店、旅行などの体験系商材)
SEAMS®(シームズ)
SEAMS®は(株)電通様が提唱した、インターネット上の衝動買いをよく表した購買行動モデルです。SEAMS®では、消費者が商品を「探す」ではなく、SNSなどのコンテンツ回遊によって偶発的に商品に「出会う」体験から購入に至るという一連の流れを以下の5段階で説明しています。
- 回遊(Surf)・・・SNSなどで情報回遊する
- 遭遇(Encounter)・・・偶然、商品/サービスの情報に出会う
- 受容(Accept)・・・商品/サービスを受け入れる(購入する)
- 高揚(Motivation)・・・商品/サービスの(期待以上の)体験で気持ちが高まる
- 共有(Share)・・・商品/サービスを他者に紹介する
レコメンド機能の精度が増しており、自分好みの記事やコンテンツがどんどん流れてくるようになった現在、目的なくSNSを眺め続ける人も増えています。その中で、それまで欲しいと思っていなかった商品/サービスを偶然発見して衝動的に買うという購買行動も増えています。その中でSEAMS®の理論をうまく活用すれば、売上UPや商品認知度の向上につなげることができます。
- 活用できる商材
- 衝動買いが可能なプチプラ系の化粧品、コスメ、雑貨、ファッション、目新しい商品など
■番外編:BtoBの購買行動モデル
これまで主にBtoCのビジネスに適用しやすい購買行動モデルをご紹介しましたが、番外編としてBtoBマーケティングに適した購買行動モデルをご紹介します。BtoBビジネスは個人が相手のBtoCビジネスとは異なり、組織で合理的な意思決定がなされるという点で、これまでご紹介した購買行動モデルではカバーできない過程をたどることが多くなります。そのため、以下にご紹介するASICAのような、BtoBビジネス用に作られたフレームワークをもとにマーケティングを考えることをおすすめします。
ASICA(アシカ)
ASICAは、BtoBビジネスに即した購買行動モデルです。以下の5段階で説明されています。
- 課題(Assignment)・・・自社の課題を認識する
- 解決(Solution)・・・課題の解決方法を探す
- 検証(Inspection)・・・解決策の有用性や費用対効果などを検証する
- 承認(Consent)・・・社内で承認を得る
- 行動(Action)・・・商品/サービスの購入/契約に至る
BtoCと大きく異なる点は「検証」段階では複数人で自社に必要かどうかの議論がされることが多いという点と、「承認」では経営層や役職者の判断を得る工程があるという点です。つまり、広告や営業などで接触した担当者と決済者が異なることも多く、そういった流れを意識したマーケティング施策の検討が必要になります。
購買行動モデルをマーケティングで活用する方法
これまで時代ごとに活用される購買行動モデルや、BtoB事業に適した購買行動モデルをご紹介しました。このようなフレームワークを活用しながらユーザー心理や行動を把握して、最適なマーケティング施策を展開することが売上UPやブランディングの成功の鍵を握っています。
なお、購買行動モデルを実務に活かすためには、単に知識として知っておくだけでは不十分です。そこで、購買行動モデルを活用してマーケティング施策の精度を高めるために意識すべき3つのポイントをお伝えします。
①商材や目的によって適切な購買行動モデルを活用する
購買行動モデルは時代や提唱者の考えによって様々なフレームワークがあるため、全てのモデルがすべてのビジネスに当てはまるわけではありません。そのため、自社のビジネスや商材と合うモデルを活用することをおすすめします。例えば、SNSで話題を広げたい・SNSと親和性のある商材ならVISASやULSSAS、リピーター獲得の施策を検討するならAIDCASなど、目的や状況に応じてモデルを選ぶことが大切です。
②各段階に応じた適切なコミュニケーション設計を行う
購買行動モデルに基づいて消費者の行動段階を可視化すれば、どの段階の人にどのようなコミュニケーションを取れば良いかが整理しやすくなります。例えば比較検討段階の人には他社商品と比べた強みや優位性を強調した広告を出したり、購入してファン化する前の人にはアフターフォローのメールを送ったりといったように、各心理状態に合わせたマーケティング施策を検討しましょう。また、全社で一貫性のあるマーケティングを行うには、広告部門だけでなく、営業やカスタマーサポート、商品企画など各部門との連携も必須です。フレームワークを共通言語として、一貫した顧客体験を設計してみてください。
③KPI設定と効果計測を行い、改善を繰り返す
購買行動モデルに基づいてコミュニケーション設計を行ったあとは、マーケティング施策の評価ができるようにKPIを設定することも重要です。例えばWeb広告やSNSで言えば「検索数」「PV数」「クリック率」「購入数」「シェアされた数」など、各段階に合ったKPIを設定し、PR効果を測定してみてください。仮に広告のPV数は増えているのに購入数が伸び悩んでいるという課題が見つかった場合、Action(購入)に引き上げる施策を増やすなど、数値をもとにして具体的な打ち手が検討しやすくなります。KPIの設定と効果分析でメッセージやコミュニケーション方法を見直しながら、最適化を目指しましょう。
まとめ
購買行動モデルは、ただの理論ではなく、広告や販促を有効にするための実践的な道しるべです。時代に合わせたモデルを理解し、自社商品/サービスやターゲットに最適なものを選び、戦略に落とし込むことで、広告の効果は飛躍的に向上します。ぜひ本記事を参考に、マーケティングに取り入れてみてください。