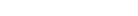- コラムトップ
- はじめての運用型広告|担当者が押さえるべき配信設計と最適化の流れ
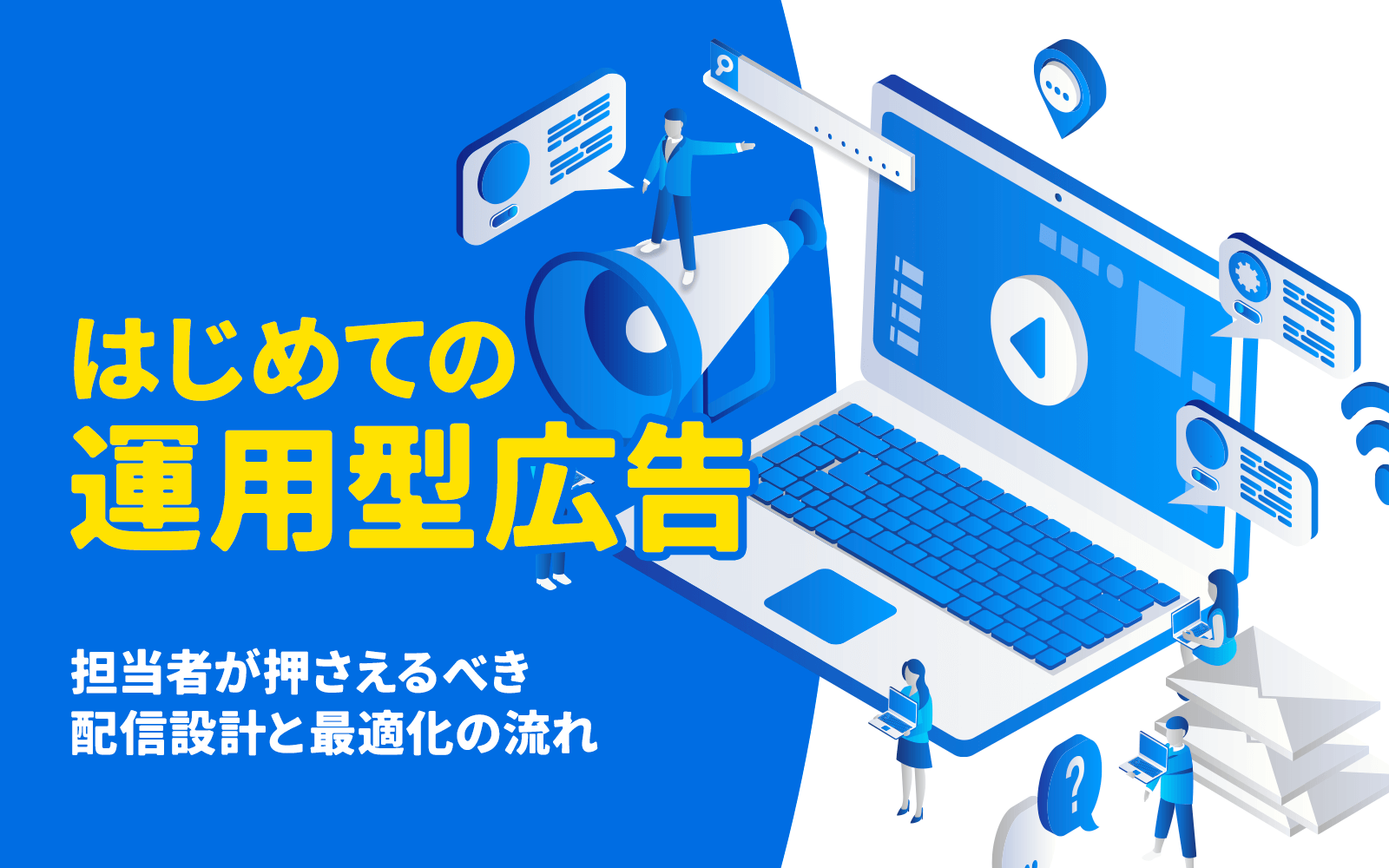
インターネット広告の中でも、今や主流となっている「運用型広告」。
私たちが日常的に目にする広告の多くも、実はこの運用型広告の仕組みで配信されています。
とはいえ、「名前は聞いたことがあるけれど、実際にはどんな仕組みで動いているのか分からない…」という企業の担当者様や広告主様も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、運用型広告の基本的な仕組みや特徴、代表的な種類、メリット・デメリットなどを、初心者の方にもわかりやすく解説します。
広告戦略を検討中の方や、これから広告運用を始める方は、参考にご覧ください。
運用型広告とは?
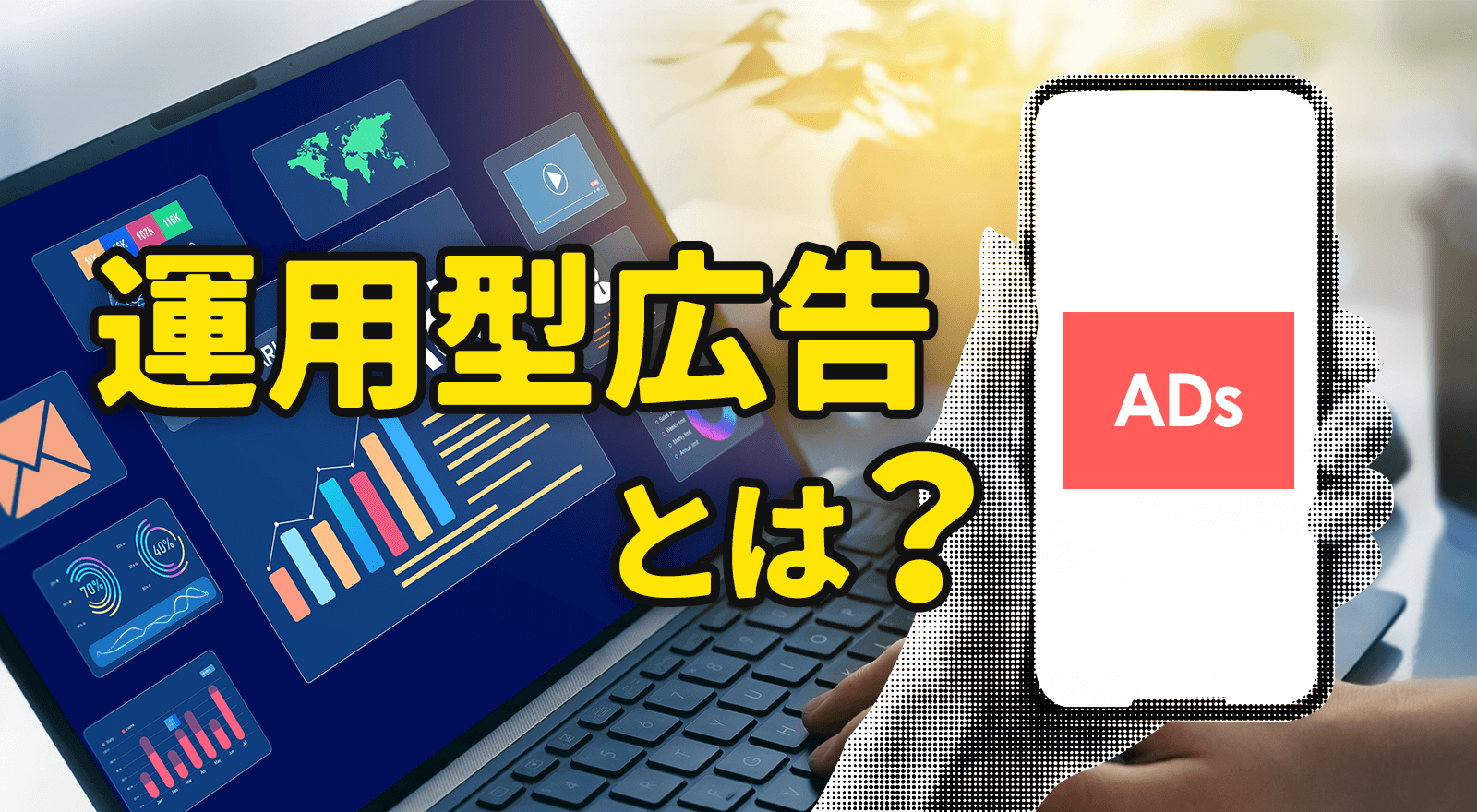
運用型広告とは、広告を配信開始した後に、様々な設定を随時調整しながら効果最大化を目指すWeb広告の総称です。設定とは、例えばターゲット設定や予算、クリエイティブなどの項目があり、それぞれを微調整して広告成果のUPを図ります。
従来の広告(新聞、テレビ、純広告など)は、出稿したら掲載内容を変えられず、一定期間同じクリエイティブで掲載し、掲載期間に対して費用を支払うのが一般的でした。
一方、運用型広告は、効果を見ながら「運用(最適化)」していくことができるため、無駄な配信を減らしながら成果を高めていくことが可能です。現在はインターネット広告の中で、主流な配信方法になりつつあります。
運用型広告の配信の仕組み
■運用型広告の配信の流れ
運用型広告は、広告主様が広告の管理画面上から直接、配信・運用を行える仕組みです。
この管理画面は、運用型広告を提供している各プラットフォーム(Google、Meta、Xなど)が発行しています。
管理画面で予算や広告クリエイティブなどの設定を行うと、その内容に基づいて広告の配信が始まります。配信の流れを大きく捉えると、以下の通りです。
①管理画面で広告の設定
広告を出すために、管理画面上で以下のような内容を設定します。
- 広告に使える予算はいくらか?(例:1日3,000円までなど)
- クリックや広告表示ごとに最大いくら払えるか?(入札単価)
- どんな人に広告を見せたいか?(例:20代女性/東京都在住/過去に特定の商品を見た人、など)
- どんな広告を見せたいか?(バナーやテキストなど、広告クリエイティブ)
②設定に基づいて、自動で広告が表示されるかどうかが決定
ユーザーがインターネットを使っているとき、Webサイトやアプリに広告を出せる「枠」が表示されます。その広告枠に対してどの広告を出すかを決めるために、一瞬でオークション(競争)が行われます。いろんな広告主様が同時に「その人に広告を見せたい!」と入札しているためです。
このオークションでは、入札金額だけでなく、「その広告がその人にとってどれだけ合っているか」も評価され、最適な広告だけが表示されます。
③ユーザーに合った広告が自動的に選ばれて表示
オークションの結果、選ばれた広告がユーザーの画面に表示されます。
例えば、過去にスニーカーを検索した人にはスニーカーの広告が表示されるなど、その人の興味や行動に合わせた広告が自動的に選ばれます。
④配信結果を分析して改善
広告を出したあとも終わりではなく、「どの広告がよくクリックされたか」「何人が商品を買ったか」などの結果を毎日チェックし、必要に応じて設定を見直します。
- 【設定の見直し例】
-
- あまり見られていない広告の画像を変更する
- 特定のターゲット層に絞って広告を出す
- 予算を増やしてもっと多くの人に広告を見せる
こうして、広告の成果を最大化するように少しずつ調整していくのが「運用型広告」の特徴です。

■運用型広告を支える3つの仕組み
このような配信が可能な背景には、以下の3つの仕組みがあります。
- オークション(RTB:リアルタイム入札)
- 1つの広告枠に対し、1表示ごとに入札が行われ、もっとも効果的と判断された広告が表示されます。
- ターゲティング
- ユーザーの属性(年齢、性別、地域)や興味・関心、Web上の行動などをもとに、広告の配信対象を細かく設定できます。
- AI(機械学習)による最適化
- ユーザーの反応データをもとに、最適な配信方法やクリエイティブをAIが自動で学習・調整します。
この3つ(オークション+ターゲティング+AI)によって、ユーザーに対して精度の高い広告配信ができるようになっています。
広告の掲載先や表示頻度は、広告主様の設定内容や、クリエイティブとターゲットとの相性など、複数の要素のかけ合わせによって大きく左右されます。そのため、配信後は管理画面でデータを確認し、ターゲティングやクリエイティブ、入札額などを随時見直すことが重要です。
オークション、ターゲティング、AIの3つの仕組みによって、今では一人ひとりに合わせた精度の高い広告配信ができるようになっています。
広告がどのサイトに、どのくらいの頻度で表示されるかは、広告主様が設定した条件や広告内容とユーザーとの相性など、さまざまな要素によって決まります。
そのため、広告を出した後は管理画面で結果を確認し、ターゲットの設定や広告の内容、入札価格などをこまめに見直すことが大切です。
このように継続的な運用が必要な特徴から、「運用型広告」と呼ばれます。
運用型広告と他広告の違い
では、運用型広告は他の広告と具体的にどう違うのでしょうか?
ここではWeb広告で従来主流だった「純広告」との比較を紹介します。
| 純広告 | 運用型広告 | |
|---|---|---|
| 掲載先媒体 | 任意のWebサイト | 様々なWebサイトの広告枠 |
| 掲載方法 | 指定のWebサイト・広告枠に 一定期間固定で掲載 |
設定に基づき 最適な掲載面に自動配信 |
| 運用の有無 | 無し (一度掲載開始したらそのまま) |
有り |
| 運用の柔軟性 | 低い | 高い |
| ターゲティング | 掲載するWebサイトの訪問者 | 性別・年齢・居住地など 細かく設定可能 |
| 費用形態 | 掲載期間や枠面積に対して固定 | 主にクリックや 表示回数ベースで変動 |
純広告は、特定のメディアの広告枠を購入し、一定期間にわたって固定で掲載される広告です。掲載先のメディアに訪問したユーザーに対して広告が固定の位置に表示される形式であり、基本的に「運用する」という概念はありません。
一方で、運用型広告は、設定した入札金額や予算・ターゲットの条件に合わせて、ユーザーに最適な広告をリアルタイムで表示します。広告は複数のサイトやアプリなどに配信され、もし思うような成果が出ない場合は、広告内容の変更や一時停止など、状況に応じて柔軟に調整することができます。
純広告に比べて、より細かいターゲティングや臨機応変な運用ができる反面、手間や専門的な知識・スキルが求められるという特徴があります。
そうは言っても、今やインターネット上で集客を行う上で運用型広告は欠かせません。ここからは、運用型広告の種類や運用のポイントなどをご紹介しますので、マーケティングの一つとして、選択肢に入れてみてください。
運用型広告の課金方式
運用型広告は、使用する広告プラットフォームによってさまざまな課金方式があります。そのため、何に対して広告費を支払うのかは、出稿前によく確認することが重要です。代表的なものを見てみましょう。
- インプレッション課金(Cost per Mille / CPM課金)
- ユーザーに対して広告が1,000回インプレッション(表示)されるごとに課金される課金方式です。主に認知拡大を目的とした広告向けです。
- クリック課金(Cost Per Click / CPC課金)
- ユーザーから広告が1クリックされるごとに課金される課金方式です。最も一般的な費用形態で、多くの運用型広告に使われています。
- 視聴課金(Cost Per View / CPV課金)
- 動画広告で、一定時間視聴された場合に課金される課金方式です。YouTube広告などで使われます。
- インストール課金(Cost Per Install / CPI課金)
- アプリ広告で使われる課金方式です。ユーザーがアプリをインストールした時点で費用が発生します。
仮にクリック課金型の運用型広告を活用し、1クリックあたり50円に設定して出稿した場合。1,000回クリックがされれば、50,000円の広告費という計算になります。
入札単価(CPC):1クリックあたり50円
クリック数:1,000回
50円 × 1,000クリック = 50,000円
運用型広告の種類と特徴
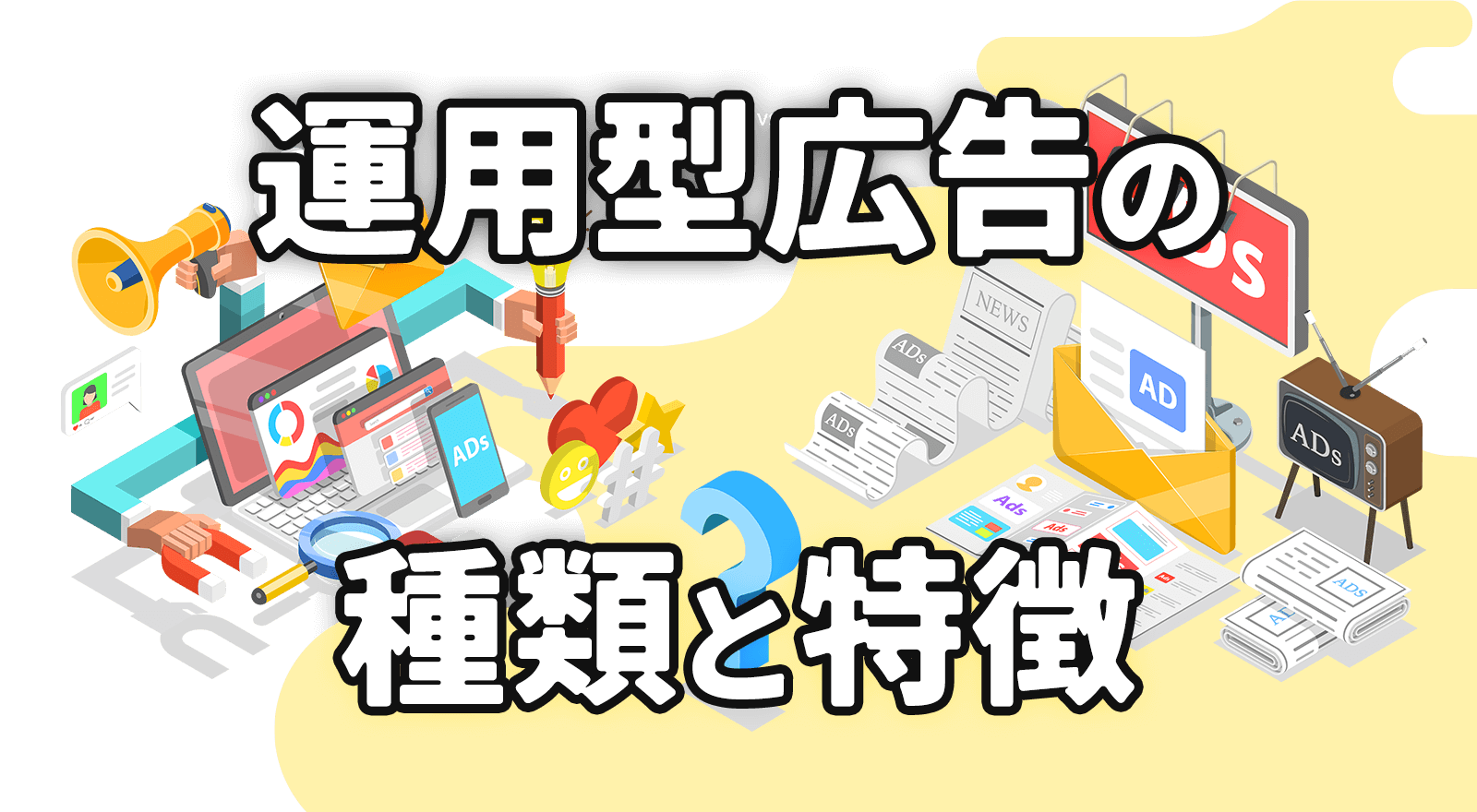
ここからは、運用型広告に該当する代表的な広告をご紹介します。
①リスティング(検索連動型)広告
GoogleやYahoo!などの検索結果に表示される、テキスト形式の広告です。ユーザーが自ら検索しているということは、すでに興味や関心がある=”顕在的なニーズ”を持っている状態と捉えられます。そのため、、購買意欲の高いユーザーへ効果的にアプローチできる広告として、幅広く活用されています。広告費用はクリックごとに発生するCPC(クリック課金)が一般的で、Google広告やYahoo!広告の管理画面上で、入札単価の設定や広告文の登録などを行います。
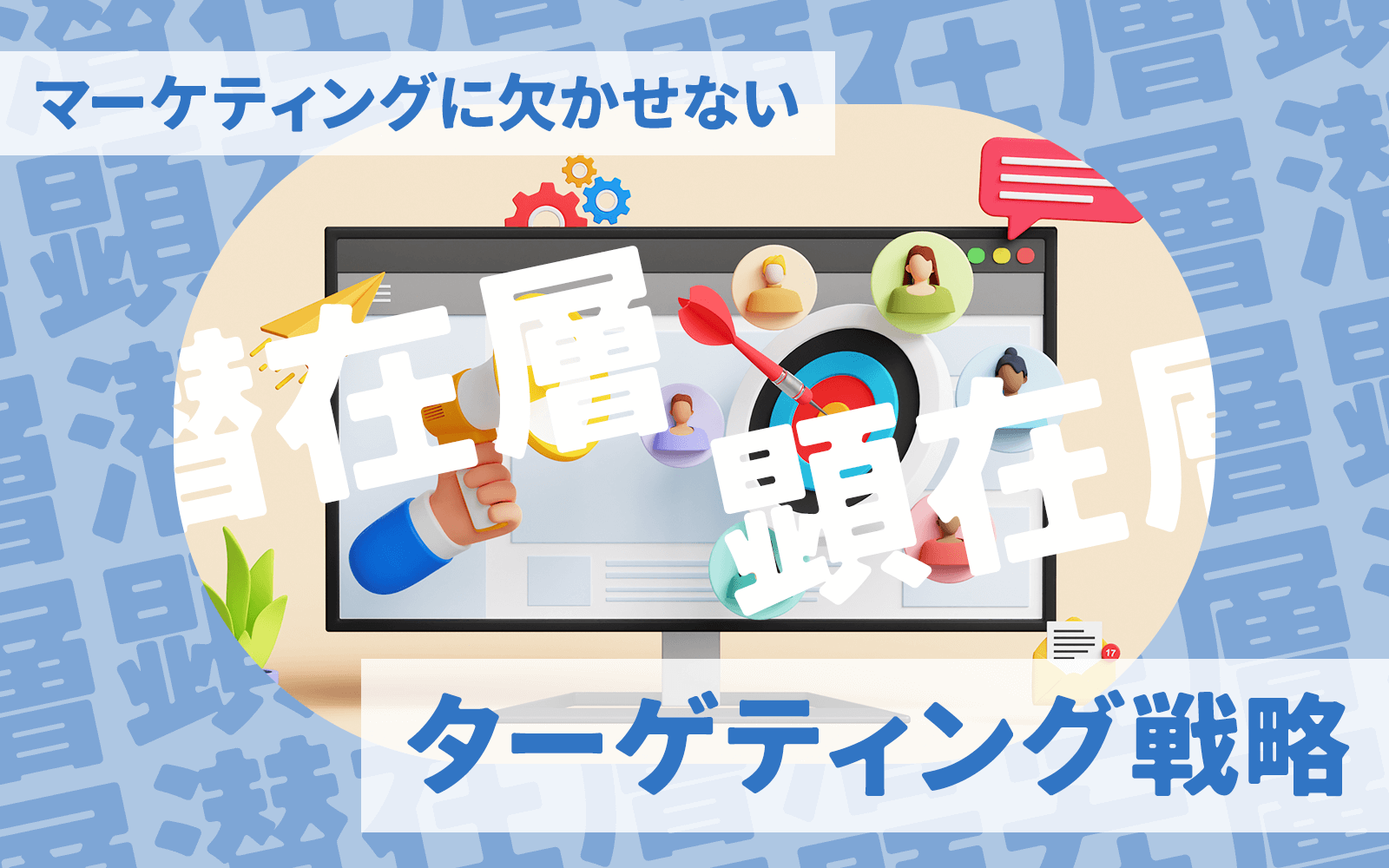
マーケティングに欠かせない「潜在層」「顕在層」の理解とターゲティング戦略
マーケティングや広告業界でよく聞く「潜在層」や「顕在層」。言葉の意味や、どういったシーンで活用するかをご存知でしょうか?潜在層や顕在層の違いを理解することは、効果的なマーケティングを行う上で欠かせません。
②ディスプレイ広告(アドネットワーク)
ディスプレイ広告は、Webサイトやアプリなど、複数の媒体に自動で表示されるバナー形式の広告です。画像や動画を使って訴求できるため、視覚的なインパクトを与えやすい点が特徴です。広告を「誰に届けるか」を決めるターゲティングと、「どのサイトやアプリに掲載するか」を決めるターゲティングの2軸があり、ユーザーの属性や興味関心、掲載面を柔軟に設定して配信できます。
③SNS広告
SNS広告は、各SNS(Instagram、Facebook、X、TikTokなど)が提供する広告の総称です。いずれも運用型広告に該当します。SNSは登録時のユーザーデータを活用できるため、精度の高いターゲティングが可能です。属性や興味・関心に基づいて細かく配信対象を絞り込めるため、マーケティングにおいて欠かせない広告手法の一つとなっています。
なお、以下の記事ではSNS広告の種類や利点をさらに細かく解説しています。

SNS広告の基本と成功ポイント|主要6大SNSの違いも解説
今やWebマーケティングに欠かせない存在となったSNS。企業の活用事例としては、公式アカウントを開設して情報を発信する方法が一般的ですが、実は広告を出稿するという選択肢もあることをご存じでしょうか?
④動画広告
動画形式で配信される広告の総称です。YouTubeで配信されるインストリーム広告、SNSのフィードやストーリーズ内の動画、ディスプレイ広告枠に表示されるインバナー広告などが含まれます。動画広告は視覚や聴覚に訴えかけることができ、ストーリーテリングにも適しているため、ブランド力の向上にも効果的です。クリエイティブの制作に手間はかかりますが、表現の幅が広い点が魅力です。
このように、Web広告の中でも一般的によく活用されている広告の多くは、「運用型広告」に該当します。用途やターゲットに応じて最適な広告手法を選定し、自社に合ったマーケティング戦略を構築することが重要です。

【関連記事】Web広告とは?12の種類とその特徴をご説明
Web広告は広告の一種で、ネット上のWebメディアやアプリ等に掲載される広告の総称です。インターネット広告、オンライン広告などとも呼ばれます。
運用型広告のメリット
運用型広告がここまで主流になった理由は、以下のようなメリットがあるためです。
①比較的すぐに集客ができる
運用型広告は、Webマーケティングの中でも比較的集客しやすいPR手法です。
たとえば、SEOやアフィリエイト広告は、効果が出るまでに時間がかかることが多く、ある程度の準備期間が必要です。一方、運用型広告は入札に勝ちさえすれば、ターゲットユーザーに対して即座に広告を表示できるため、即効性に優れています。
広告を出稿する目的にもよりますが、短期間で効率的に集客したい場合に適した手法といえるでしょう。
②効果測定がしやすい
運用型広告は、管理画面上で広告の効果をリアルタイムに確認することができます。クリック率やコンバージョン率など、日々蓄積されるデータを分析しながら、単価やクリエイティブをすぐに調整できるため、効果の最大化を図りやすく、柔軟な配信が可能です。
③ターゲティング精度が高い
年齢・性別・興味関心など、細かく配信対象を設定できるため、自社の商品/サービスのターゲットに対して効率的にアプローチできます。あまりにターゲットを絞りすぎると、思わぬ顧客を逃してしまう可能性もありますが、逆に言えば、そうした「潜在顧客層の掘り起こし」を検証するテストマーケティングにも活用できます。
④予算調整・配信停止も柔軟にできる
予算や期間の変更、広告の一時停止なども随時対応可能です。広告主によっては、在庫状況や予算の都合などでPRする商品の販売状況が変化することもありますが、運用型広告であれば、そのような状況の変化にも管理画面から即座に対応できます。
⑤少額から始められる
運用型広告の多くは、数千円からでも広告配信が可能です。マーケティング予算が限られている中小企業にとっても導入しやすく、気軽に始められる点も大きなメリットです。
なお、アフィリエイト広告は少し時間がかかることを説明しましたが、運用型広告と組み合わせることで、比較的早く効果を出す手法も存在します。ご興味がある広告主様は以下の記事も参考にご覧ください。
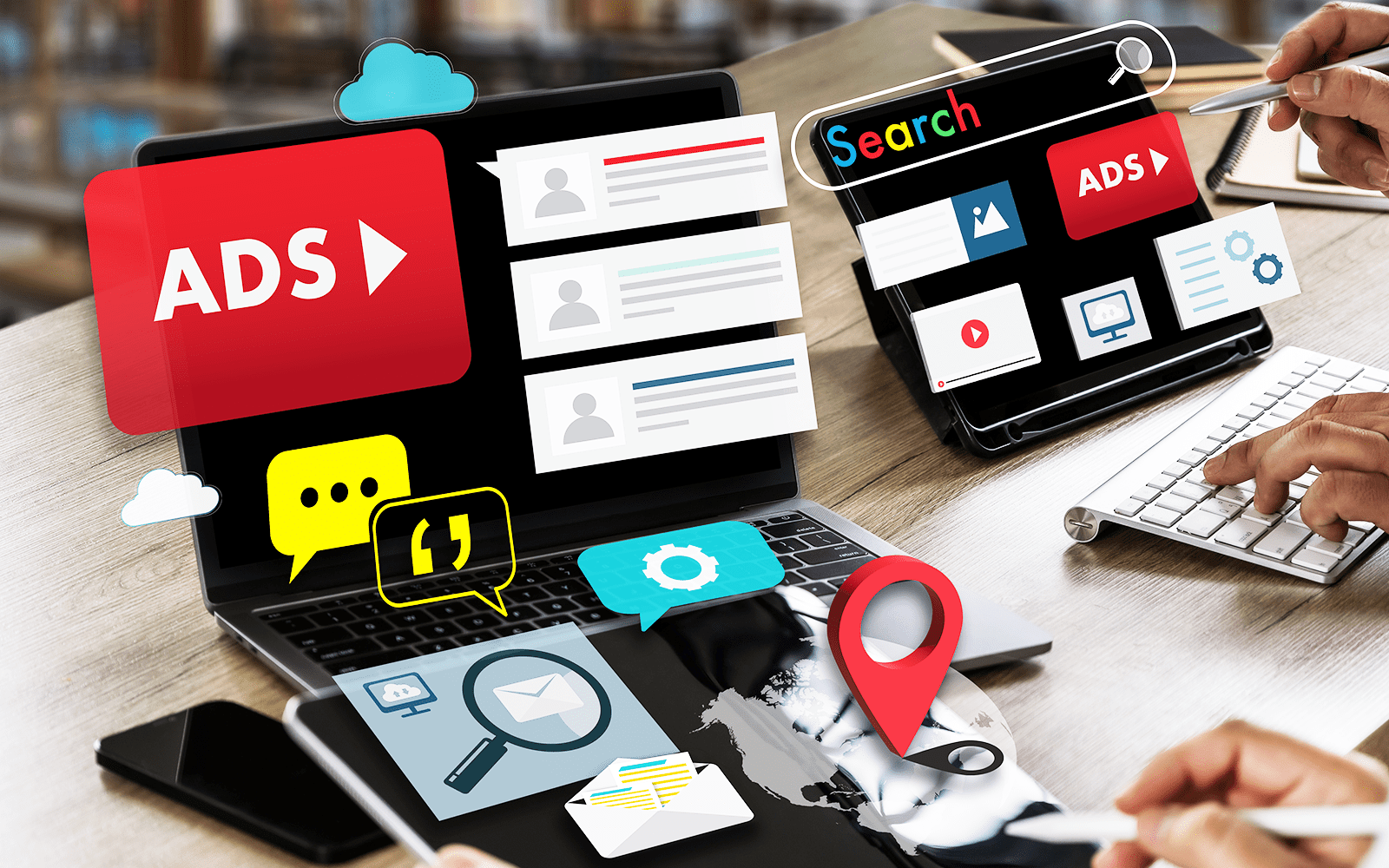
アドアフィリエイトとは?
アフィリエイト広告×アド出稿のメリット・デメリットを解説
アフィリエイト広告を展開していると、稀に聞く言葉「アドアフィリエイト」。アフィリエイト自体もアド(広告)なのに、どういう意味だろうと思ったことはないでしょうか。
運用型広告の注意点
メリットも多い反面、運用型広告にはいくつかの注意点もあります。
①知識・経験がないと成果が出づらい
運用型広告を効果的に活用するには、一定の専門知識や運用スキルが求められます。商品やサービスの購入層とターゲティングがズレていれば成果につながりませんし、設定ミスによって思わぬコストが発生することもあります。
②初期は成果が安定しにくい
出稿初期は、広告の効果を安定させるまでに試行錯誤が必要です。少額で始められるのは運用型広告のメリットですが、予算を絞りすぎると十分なデータが集まらず、最適化や成果拡大につなげにくくなる場合があります。また、効果が出るまでの間は一時的に赤字になるケースも少なくありません。中長期的な視点でデータを蓄積しながら運用を続けることが大切です。
③誤設定で無駄なコストがかかる可能性
ターゲティングや配信設定を誤ると、無関係なユーザーに広告が表示されてしまい、本来得られるべき成果を逃すだけでなく、不要な広告費がかかるリスクもあります。
④運用にリソースや時間がかかる
運用型広告では、データ確認や効果改善を継続的に行うことが欠かせません。データ分析や入札単価の調整だけでなく、新しい広告クリエイティブの制作・入稿、訴求内容の見直しなど、さまざまな作業が発生します。これらの業務を継続的に行い、広告効果を最大化していくためには、一定の人的リソースや運用の工数を確保することが重要です。
自社運用?代理店を利用する?
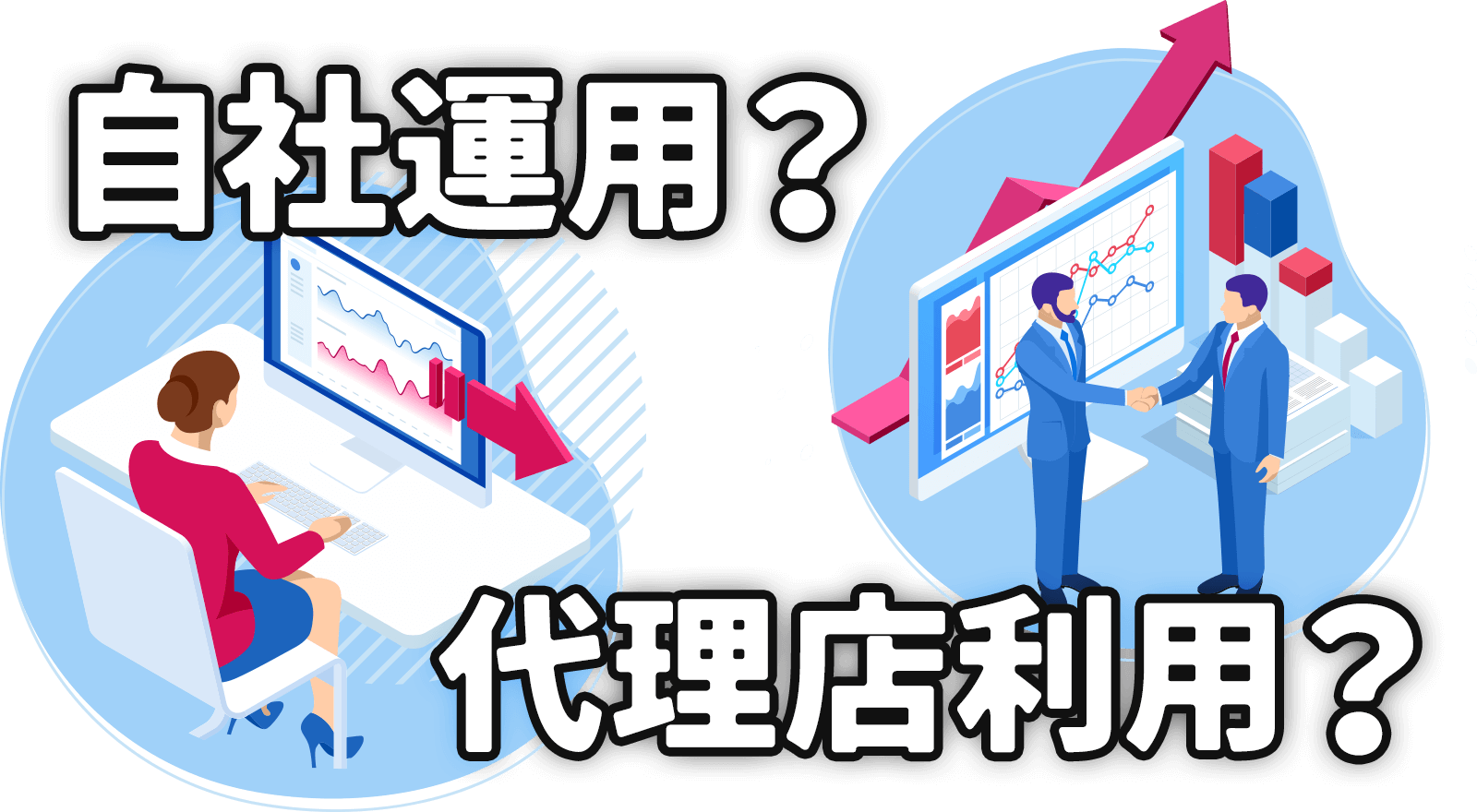
運用型広告を出稿する際には、主に2つの運用方法が選択肢としてあります。「自社で運用する(インハウス)」もしくは「代理店に任せる」の2パターンです。それぞれのメリットやデメリットを挙げますので、運用を開始する際の参考にしてみてください。
- 【自社運用のメリット・デメリット】
-
メリット デメリット コストが抑えられる ノウハウや人的リソースが必要 運用ノウハウが社内に蓄積される 試行錯誤に時間がかかる
- 【代理店運用のメリット・デメリット】
-
メリット デメリット スピーディに成果を出しやすい 手数料がかかる 社内リソースや時間的負担を軽減できる 依頼先との連携・コミュニケーションが必要
自社で運用する場合、専門的な知識やスキルがないと、成果を出すのが難しい場合があります。ただし、外注費がかからない分、広告コストを抑えられる点は大きなメリットです。
代理店に依頼する場合は手数料が発生するものの、プロのノウハウによって短期間で成果を上げやすいという利点があります。
代理店手数料については広告費の20%ほどが相場と言われています。
ただし、広告費に対する手数料方式や固定料金方式、成果報酬型など、様々な料金体系がありますので、代理店に問い合わせてよく確認しておくと良いでしょう。
自社の状況や目的に応じて、最適な運用体制を選ぶことが重要です。
運用型広告で効果を出すポイント
成果を最大化するには、ただ広告を出すだけでは不十分です。以下のようなポイントが重要になります。
①明確な目標(KPI)を設定する
広告を出稿する際はまず「どんな成果を目指すのか」という明確な目標(KPI)を設定することが大切です。例えば、売上アップを目的とする場合は「コンバージョン数(申込数や購入数)」、認知度を高めたい場合は「表示回数」や「動画の再生数」などが指標になります。
運用型広告は日々広告費が発生する仕組みのため、目標があいまいなままだと効果を正しく評価できず、結果的に無駄な出稿費につながることもあります。 以下の指標を参考に、自社の目的やフェーズに合わせてKPIを設定してみましょう。
| 目的 | 主なKPI |
|---|---|
| CV獲得 |
CV数 CPA ROAS CVR |
| 認知拡大 |
インプレッション 動画再生数 リーチ数 |
| サイト誘導 |
クリック数 CTR セッション数 |
| リピート促進 |
LTV 再訪率 顧客単価 |
②ターゲット層を明確にする
運用型広告では、ターゲットユーザーを明確にしたうえで出稿することが非常に重要です。広告を表示させるターゲティングの設定や、制作すべきクリエイティブにも大きく関わってくるため、ここが曖昧だと広告の効果に悪影響を及ぼします。
商品やサービスのターゲットが定まっていない、あるいは「誰に広告を見せるべきか分からない」という場合は、以下の記事を参考にしながら、狙うべきターゲットを検討してみてください。
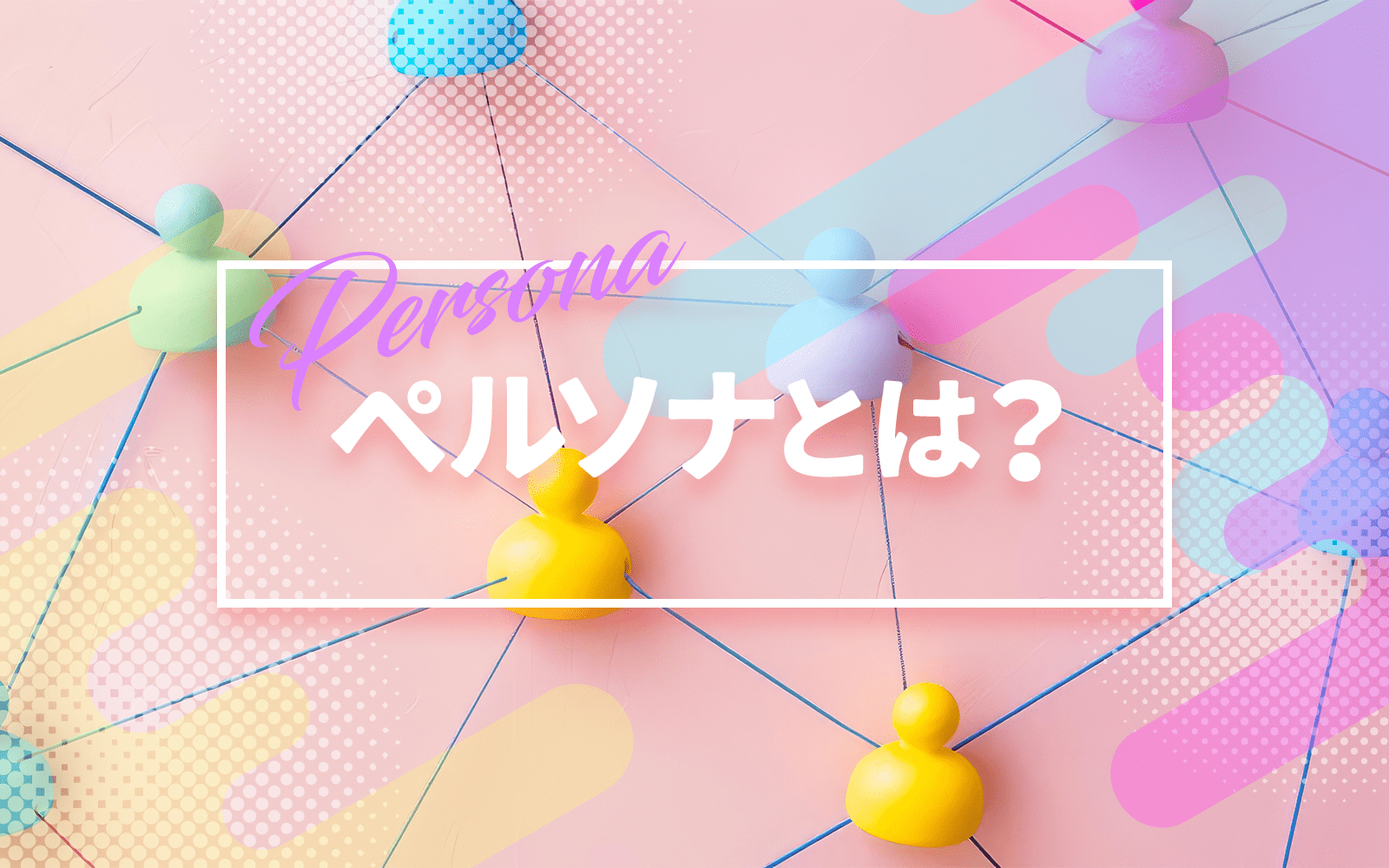
ペルソナとは?
BtoCマーケティングで使うペルソナの概要と、メリットや設定する手順を解説
「ペルソナ」の設定は、企業が商品開発やPRを行う上で欠かせないプロセスです。顧客や見込み客の悩み・ニーズを正確に把握しながら事業を展開すれば、購入や契約、リピーター獲得等が効率よく進む可能性があります。
③LPやバナーなどクリエイティブの質を高める
LPやバナーなどの広告素材のクオリティを高めることも、効率よく広告効果を上げるための重要なポイントです。多くの場合、素材は1種類ではなく、ターゲット層や訴求内容ごとに複数パターンを用意して出稿し、ABテストで効果を検証するのが一般的です。
ユーザーに「これは自分に向けられた広告だ」と気づいてもらうことが、クリックや申込みといったアクションにつながるためです。たとえば、男女でバナーを分けたり、装飾やキャッチコピーを変更したりと、ユーザーの反応を見ながら改善を重ねてみてください。
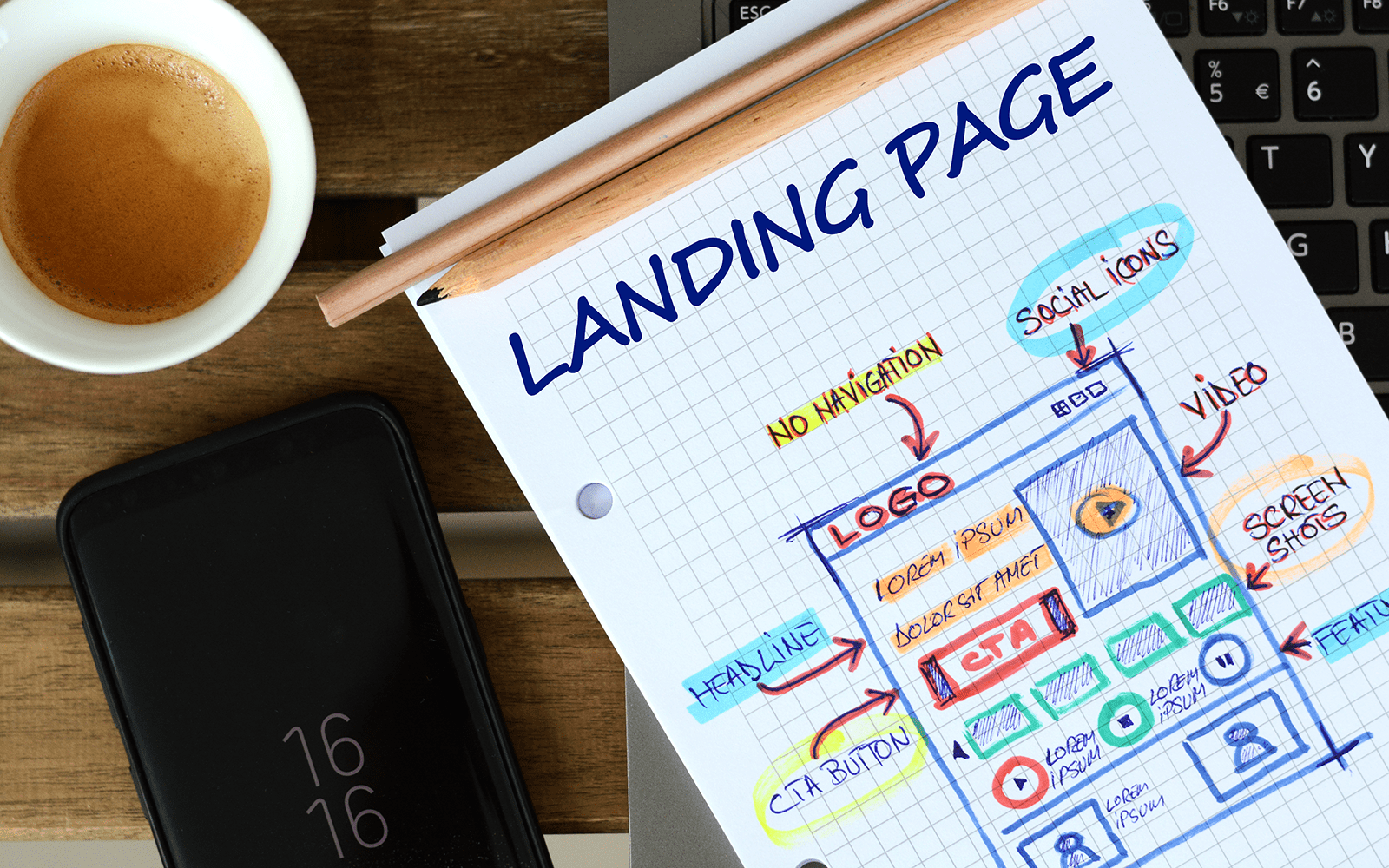
効果的な広告を運用する為のLP構成と制作方法
前回の記事ではLPの基本的な知識と、メリット・デメリットについて触れました。今回は、LPの作成を検討している方に向けて、構成や作り方の手順について解説します。
④効果を見て継続的に改善する
運用型広告では、出稿後の効果測定と継続的な改善が最も重要な工程です。表示回数やクリック数など、一定量のデータが蓄積されたら、効果の低い広告は停止やバナーの変更を検討したり、逆に効果の高い広告には出稿量を増やすなど、微調整しながらPDCAを回しましょう。
また、一時は効果が高いと評価できる広告であっても、継続して出稿し続けると徐々に効果が落ちてくるケースもあります。油断せず、常にデータを確認しながら改善を続けることが重要です。
まとめ
運用型広告は、少額から始められ、効果を見ながら柔軟に改善できるのが魅力の広告です。
集客にお困りの広告主様や、出稿を検討している広告主様は本記事を参考にして、Webマーケティングに運用型広告を取り入れてみてください。